どんなに可愛い我が子でも、イライラしてつい怒ってしまう、そして怒ってしまったことを後悔して自己嫌悪に陥る。育児をしているとそんな経験はあるのではないでしょうか。
もちろん頭ごなしに怒ることはダメだとわかっていても心に余裕がないときに怒ってしまうこともあると思います。
今回はそんなイライラに対応できる「アンガーマネジメント」について紹介したいと思います。
怒られることに対する子どもへの影響
怒りの強度(怒鳴りつけるなど)や頻度により影響の大きさは変わってきますが次のようなリスクがあります。
キレやすくなる
親の姿をみて子どもは感情のコントロールを学びます。いつも怒鳴ったりしていれば子どももそういうものだと思って怒鳴るなどの感情表現を学んでしまいます。
自己肯定感が下がる
怒られてばかりいると「自分は何をやってもダメ」と思うようになり、自己肯定感を育むことがができません。自己肯定感が下がると積極性や主体性という大切な能力を伸ばすのが難しくなります。
親に何も話さなくなる
怒られてばかりいたら、怒られることが怖くなり、親に自分のことを話さなくなるようになります。小さいうちは子どもは親からコミュニケーションを仕方を学びます。
親と話す機会が減っていくとコミュニケーションを学ぶ場がなくなり、小学校や中学校になってから周りとのコミュニケーションに苦手を感じるようになり、不登校や引きこもりなどのリスクが高まります。
このように、子どもを怒って育てると大人になってから豊かな人生を送るために重要な能力を奪うことになってしまいます。
怒ることはダメなのか
怒られて育った子どもへの影響を考えると怒ることがダメなのはわかったと思います。それでもイライラして怒りたくなってしまうときもありますよね。親も結局は一人の人間。感情があります。怒りたくなることもあって当然です。でも、その「怒り」をそのまま子どもにぶつけるのはダメ。
冒頭触れたアンガーマネジメントを実践してしっかりと子どもと向き合うようにしてください。
でもだからと言って危険なことをしたり、相手が嫌がるようなことをしても何も言わないのはまた違う話です。
大切なことは頭ごなしにおこるのではなく、悪いことはしっかりと「叱る」ということです。
怒りが自分に与える影響
先程は怒りが子どもに与える影響を見ていきました。ですが、イライラや怒りは自分自身にも影響します。
健康への影響
怒りやストレスが長期間続くと、心身の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。過度な怒りは高血圧や心臓病などの問題などを引き起こすリスクを増加させることがあります。アンガーマネジメントを行うことで、心身の健康を守ることができます。
人間関係への影響
怒りっぽい人は、周囲の人々との関係に悪影響を与えることがあります。怒りが原因で友人や家族との関係が悪化することもあります。アンガーマネジメントを実践することで、より良い人間関係を築くことができます。
仕事への影響
職場での怒りは、仕事のパフォーマンスや効率に影響を与えることがあります。怒りっぽい態度や行動は、同僚や上司との関係を損なうだけでなく、自身のキャリアにも悪影響を及ぼす可能性があります。アンガーマネジメントを実践することで、仕事のストレスを軽減し、生産性を向上させることができます。
アンガーマネジメントとは
アンガーマネジメントとは、怒りやイライラといったネガティブな感情を適切に管理し、コントロールするための技術や手法のことです。怒りは人間の感情の一部であり、それ自体が悪いものではありません。
しかし、怒りが過度になると冷静さを欠くことや、他者に対して攻撃的な態度を取ることがあります。アンガーマネジメントは、こうしたネガティブな感情を理解し、適切に対処するための方法です。
また、アンガーマネジメントは怒りを我慢するということではありません。怒る必要のあるときには上手に「叱る」こともアンガーマネジメントの一つです。
アンガーマネジメントの具体的な実践方法
6秒待つ
ムカッときたときには「6秒間」待ちましょう。怒りの感情のピークは6秒ほどと言われているためです。でも強いストレスを感じて今にも怒鳴ってしまいそうな状況で6秒も我慢するのって結構難しいです。
そんなときに試したいのが「コーピングマントラ」その場で自分を落ち着かせるための魔法のフレーズを心のなかで唱えるテクニックです。フレーズ自体は自分が一番落ち着ける言葉で構いません。例えば「大丈夫、大丈夫」「怒らない、怒らない」など。また言葉でなくても構いません。手をグーパーグーパーとしたり、大きく深呼吸してみたり。自分が一番落ち着くやり方を見つけてください。
大切なことはフレーズを唱える(仕草を行う)ことによりその場で気持ちを落ち着かせるかどうかです。
その場を一旦離れる
子どもを怒ってしまいそうになったとき、状況的に許せば一旦物理的に離れるのはいかがでしょうか。その場を一旦離れることにより怒りを早く落ち着かせることができます。一人になって深呼吸やストレッチをして心を落ち着かせてみてください。
ただし、実際にはママと子供だけという状況だと難しいこともあると思ういます。コミュニケーションが取れるくらいのお子さんであれば、「冷静になりたいから10分だけ一人にさせて」と話して、不安にならないように必ず戻ってくることを伝えるようにしましょう。
アンガーログ
これは名前の通り怒りの記録です。イライラしたこと、怒ったことを記録しておきます。あとで見返すと自分の怒りの癖や傾向を掴むことができます。記録を続けるのは面倒かもしれませんが、自分の心や子供の成長のためにもしっかりとアンガーログを取ってみてください。
上手な叱り方とは
ここまで怒りのコントロールの手法を解説してきました。ですが、子どもの行為によって自分がイライラしたのであれば、その行為もやめさせる必要がありますよね。ここで大切なのが上手な「叱り方」です。
感情的に叱らない
イライラした時にそのまま叱ってはだめです。先程の6秒耐えて少し冷静になってから対処しましょう
事実に対して叱る
今、この場でのことに対して叱りましょう。昔のことを引っ張り出してきても意味はありません。
ちゃんと目を見る
叱るときはしっかりと子どもの目を見ましょう。何かをしながらではなく、しっかりと子どもに向き合い、目を見て叱りましょう。目を見て叱ることにより気持ちが伝わりやすくなります。
I(私は)メッセージを使う
「ママ(パパ)はこうしてほしかった」とI(私は)メッセージで伝えるのも効果的です。You(あなた)メッセージだと子どもの行いに目が言ってしまい、「なんで片付けないの!」などになってしますが、Iメッセージだと「ママは片付けてほしいな」などママの気持ちにフォーカスします。
まとめ
今回はアンガーマネジメントの理論を活用した子育てのイライラ対処法を紹介しました。どうしてもイライラしてしまう場合、紹介したアンガーマネジメントをぜひ活用してみてくださいね。
また、今回は育児をされるママ・パパ向けに記載しましたが日常のコミュニケーションやビジネスコミュニケーションの場でも有効ですので、ぜひ参考にしてみてください。
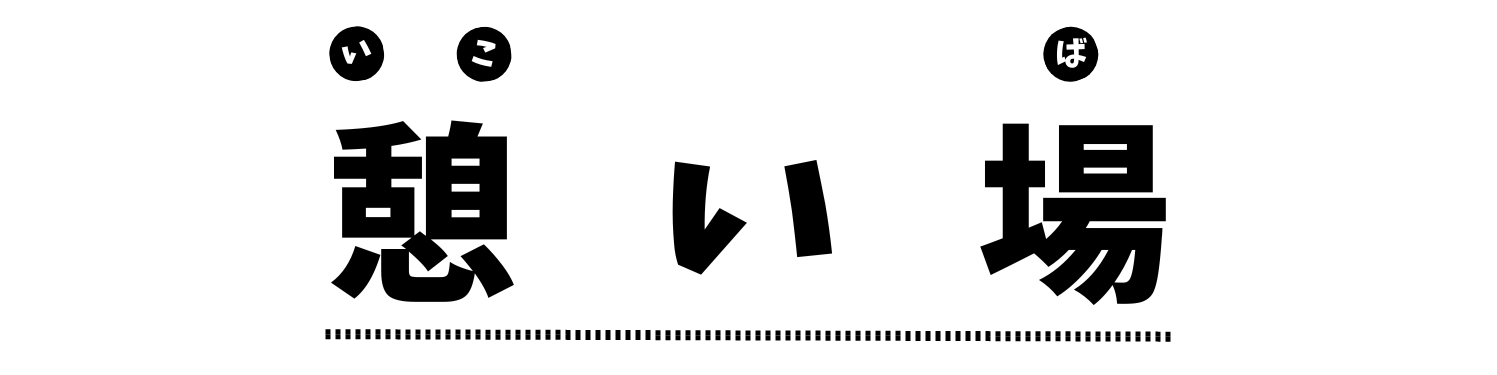
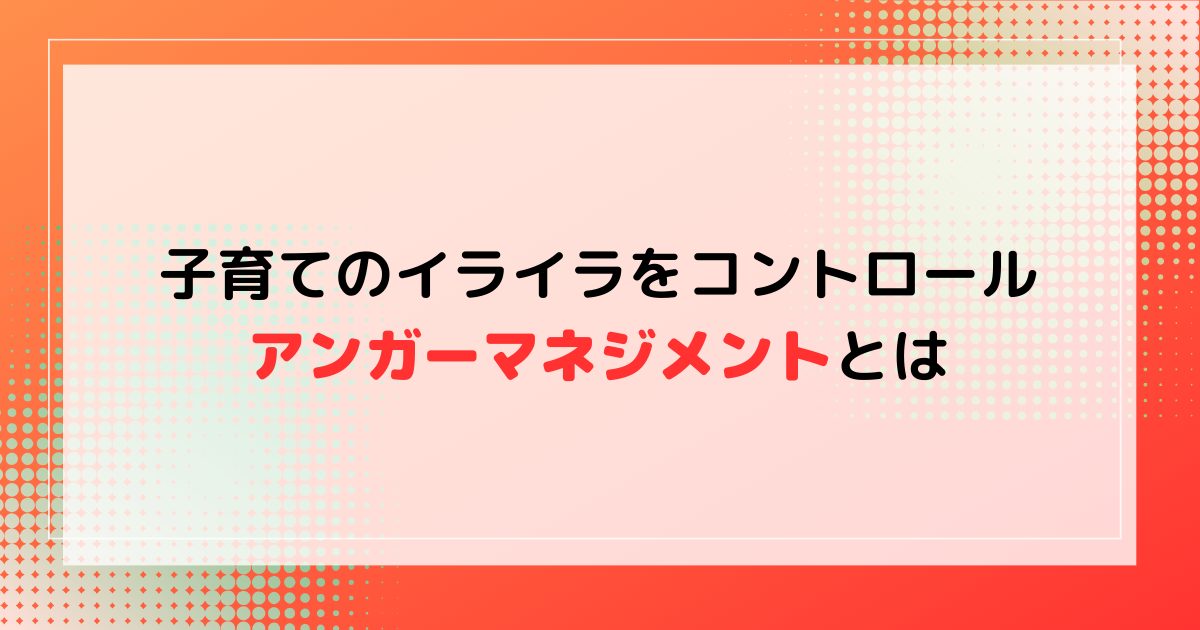

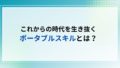
コメント