ゆでガエル理論とは?
気がついたときには大惨事。
あなたの身の回りにも、そんな経験はないでしょうか?実はこれ、ゆでガエル理論といいます。人間は急激な変化に付いていけません。だから、拒否反応を起こし、危険を免(まぬか)れる事ができます。しかし、徐々に変化していくと、人間は変化に気づかないのです。
これを寓話に例えて「ゆでガエル理論」といいます。
ゆでガエル理論は1998年に有斐閣アルマより出版された「組織論」で紹介され、有名になりました。
「カエルは熱湯の入った桶に入れられると、
死にたくないから桶から飛び出してしまう。
しかし、水の入った桶に入れられ、
それをストーブにかけて
ゆっくり暖めてやる。
そうするとカエルはいつの間にか、
ゆでられて死んでしまう
引用:組織論 桑田耕太郎・田尾雅夫著
本来は経営組織論の話で引用されています。徐々に業績が悪くなると、気づいたときには手遅れになるということを指摘しています。
身の回りで起こるゆでガエル
この「ゆでガエル理論」は組織の視点から見たものですが、個人でも言えることです。
人間は現状に満足してしまうと、向上心がなくなってしまいます。スマートフォンがあっという間に普及したように、生成AIがあっという間に進歩したようにテクノロジーの進歩は目まぐるしく変わります。
技術や環境がこれだけ大きく変わるのに、私たち人間が変わらないで良いわけがないのです。しかし、先程お伝えしたように、人間はどうしても満足すると現状を維持しようとします。
※現状維持バイアスと言います。
ゆでガエルにならないためには?
水温を測る
茹で上がってしまう前に、今、何度かを把握しましょう。温度計のように数字で測れるものではないかもしれません。
社会の状況と、自分自身の状況を照らし合わせましょう。知識やスキルが追いついているか、しっかり見極めてください。客観的に見ることが大切です。
あなたが今後も求められる人材かどうか、第三者に話を聞いてみるのもよいでしょう。
実はゆでガエルは作り話?
色々と話しをしましたが、実はこのゆでガエル理論、科学的には全く根拠がないのです。実際には徐々に温度を高くしていっても、カエルは環境変化に気づいて熱くなる前にお湯から逃げ出します。また熱湯に放り込んだら死んでしまいます。決して真似しないでください。
おそらくこの話が受け入れられたのは、現代人にとって理解しやすく、戒めとなるような話だったことから深く広まったのではないでしょうか。
まとめ
ゆでガエル理論自体は根拠のない寓話でしたが、説得力もあり、ビジネスのヒントになります。
今自分を取り巻く環境はどうなのか、しっかりと分析し「気づいたときにはもう手遅れ」という状況にならないようにしましょう。
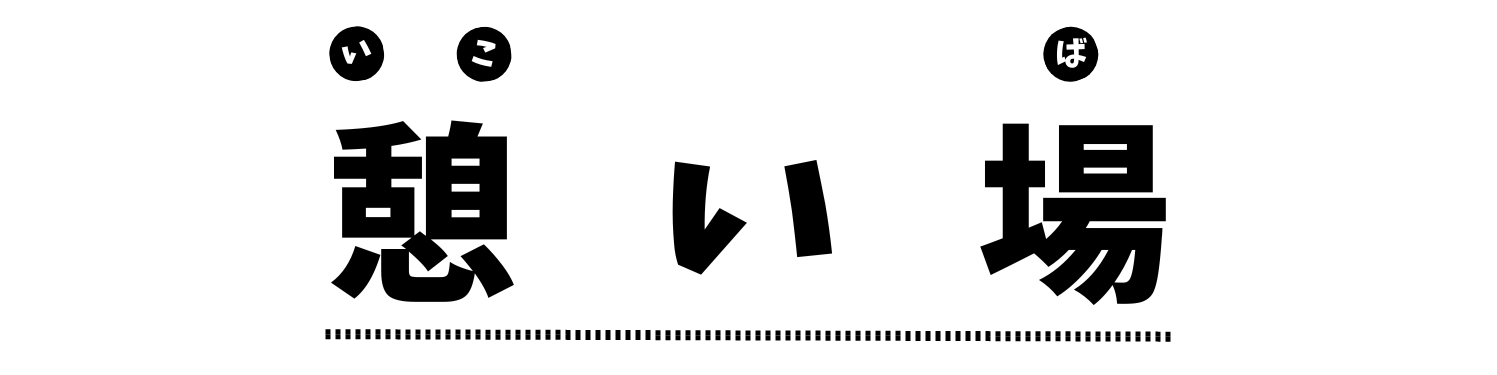
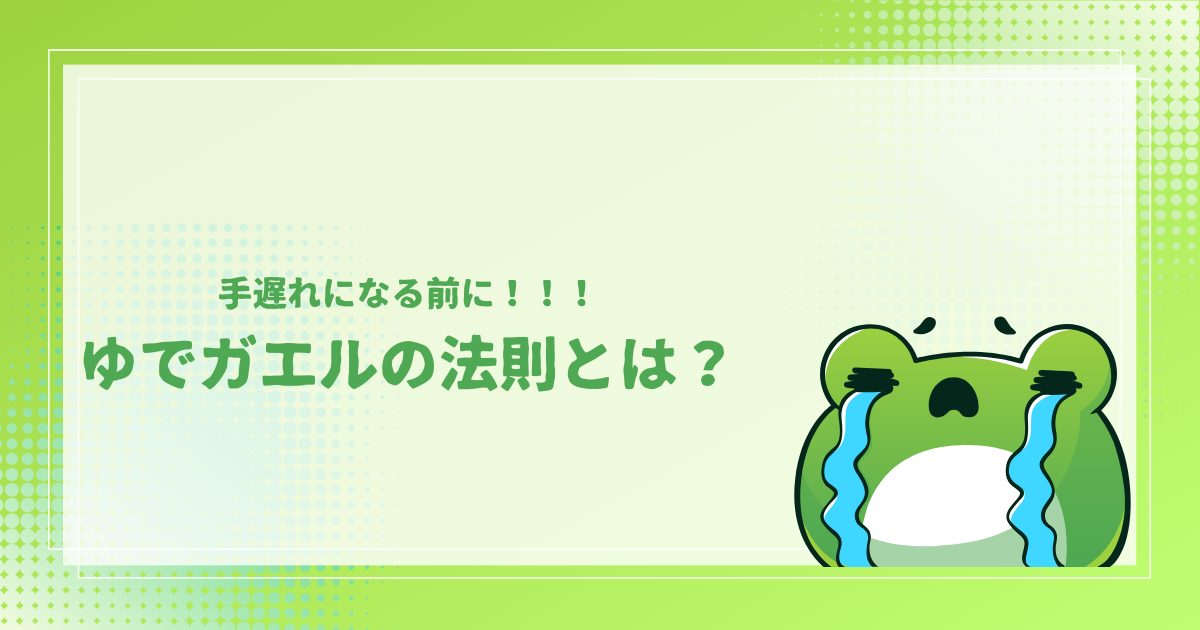

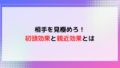
コメント